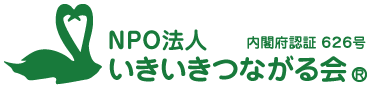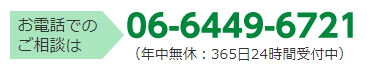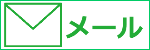お墓を無くそうかと検討されている方にとって、墓じまいの補助金は気になるキーワードではないでしょうか。
近年、少子高齢化やライフスタイルが変わっていく中で、樹木葬やその他色々な方法を選択する方が増えています。
ですが今までご先祖様がいらっしゃった墓石の撤去や改葬等、思いのほか多くの費用が掛かる為、経済的な負担が懸念されます。
そこで注目されているのが、自治体が提供する墓じまいの補助金です。
この制度を利用する事で、費用の一部を補助してもらえる可能性があります。
ただし補助金の有無や支給条件、申請方法は自治体で変わって来るので、事前の情報収集が重要です。
本記事では墓じまいの補助金は本当にもらえるのか?という疑問にお答えし、補助金の概要や申請条件、手続きの流れ、実際に補助金を提供している自治体の事例等を詳しく解説します。
経済的な負担を軽減し、安心して手続きを進められるよう、是非参考にして下さい。
墓じまいの補助金とは?どんな制度なのか分かりやすく解説

墓じまいの補助金とは、費用を自治体が一部支援してくれる制度の事です。
墓石は撤去や改葬先への移転費用等、決して安くはない出費が伴います。
そこで経済的な負担を減らす為に、多くの自治体では一定の条件を満たす方に対して補助金を交付しています。
しかしこの墓じまいの補助金は全国一律の制度ではなく、内容や支給条件は自治体で異なる為、正しく理解しておく事が大切です。
ここでは制度の仕組みや目的、そして基本的な仕組みについて分かりやすく解説していきます。
墓じまいとは何か?補助金との関係を知っておこう
現在あるお墓を撤去し、そこに埋葬されている遺骨を他の場所に移す(改葬する)手続きの事を指します。近年では、お墓を継ぐ人がいない、遠方で管理が難しい、子供に負担を掛けた無いといった理由から、この方法を選ぶ方が増えてきました。
とはいえ、お墓を無くすという事を考えるとさまざまな工程と費用が伴います。
例えば墓石の解体・撤去費用、遺骨の取り出しと洗浄、改葬先(納骨堂や樹木葬、合祀墓等)への移転費用、役所への改葬許可申請、そして宗教的な儀式やお布施等、細かな出費が重なります。
ここで注目されるのが墓じまいの補助金という制度です。
経済的な負担を減らす事が出来るのですが、一定の条件のもとで自治体が費用の一部を補助する制度になります。
墓じまいの補助金は、特に過疎化が進む地域や、無縁墓の増加に悩む自治体等が積極的に導入しており、個人の決断を後押しするものとなっています。
こういった制度が現在あるので、事前に制度の有無や対象条件を調べておけば、無理のない形で墓じまいを進める事が可能になります。
自治体によっては申請時期が決まっている予算が限られている改葬先に一定の条件があるといったケースもある為、早めの情報収集がカギとなります。
なぜ墓じまいに補助金が出るのか?制度の背景
そもそも、なぜ墓じまいの補助金のような制度が存在するのでしょうか?その背景には、日本社会が抱える複数の問題が深く関係しています。
まず第一に、少子高齢化と核家族化の進行があります。
地方では特に、後継者のいないお墓が年々増えており、誰も管理しなくなった無縁墓が社会問題となっています。
これにより、墓地全体の景観や衛生環境が損なわれ、霊園管理者や自治体にとっても深刻な課題となっているのです。
また都市部では遠方にある実家の墓を管理出来ない将来の子供の世話になりたく無いといった理由からもうお墓という形を辞める方が多いのです。
こうしたニーズに対応しつつ、無縁墓の増加を防ぐ為、自治体は墓じまいの補助金という制度を設け、経済的な支援を行っています。
さらに、自治体側にもメリットがあります。
墓地のあと整理された区画を再活用出来る事で、霊園全体の維持管理コストを抑えられたり、環境整備が進んだりする事もあって、インセンティブがあるのです。
特に過疎化の進む地域では、人口減少に伴って放置された墓地が増えやすく、これに歯止めをかける目的で、墓じまいの補助金を積極的に交付している自治体も存在します。
つまり、墓じまいの補助金は単なる個人への支援策ではなく、地域全体の墓地管理や景観保持、文化財的な保護を含めた長期的な政策の一環として導入されているのです。
こうした制度の背景を理解する事で、なぜ自治体が補助金を出すのか、どのような狙いがあるのかが見えてくるはずです。
墓じまいの補助金がもらえる条件とは?

墓じまいの補助金は、誰でも自動的にもらえるわけではありません。
補助金を受け取る為には、各自治体が定めた条件を満たす必要があります。
たとえば、その地域に住民票がある事一定の年齢以上である事や、遺骨の改葬先が決まっている事等、条件の内容は自治体によってさまざまです。
この章では、墓じまいの補助金を申請するにあたっての基本的な条件や、実際にどのような人が対象になるのかを詳しく見ていきましょう。
事前に確認しておく事で、申請の手間やトラブルを避ける事ができます。
補助金対象になる墓じまいのパターン
墓じまいの補助金を受け取るには、まずどのような事が補助金の対象になるかを理解しておく必要があります。誰にでも支給されるわけではなく、自治体が定めた一定の条件やパターンに該当するケースのみが対象となります。
主に以下のような場合が、補助金の対象とされる傾向にあります。
■ 公営墓地・共同墓地 市町村が管理する公営墓地や地域の共同墓地で、後継者がいない、または高齢の為に維持管理が困難なケースは、特に墓じまいの補助金の対象となりやすいです。
自治体の保全管理負担を軽減出来るという観点から、積極的に支援される事があります。
■ 管理が放置されている無縁墓の整理 無縁墓となってしまった墓石を撤去・整備する場合にも補助対象になる事があります。
周囲の景観や安全性への影響を防ぐ目的から、自治体が支援制度を設けているケースが多いです。
■ 過疎地域や中山間地域 人口減少が進む地域では、墓地そのものの維持が困難になっている現状があり、違う土地として活用する動きが強まっています。
こうした地域では、墓じまいの補助金が比較的手厚く設定されている事もあります。
■ 地域振興や再整備を目的とした墓地の統廃合 地域によっては、霊園や墓地の再整備の一環として、既存の古い墓を移転・改葬する事を条件に交付する制度が用意されています。
これは公共事業の一環としての墓じまいにあたります。
ただし上記のようなパターンでも、遺骨の改葬先が決まっていない場合や、書類が不備な場合は補助金の対象外となる事もある為、注意が必要です。
墓じまいの補助金を確実に活用するには、まず自治体が公開してるホームページや窓口で、どのようなケースが対象になっているかを必ず確認する事が大切です。
申請出来る人の条件(個人/団体の違い等)
墓じまいの補助金を活用する為には、誰が申請出来るのかという条件を正しく理解しておく事が大切です。補助金制度は誰にでも一律に与えられるものではなく、申請資格の有無によって受給出来るかどうかが決まります。
■ 基本的には“墓地使用者”が対象 多くの自治体では、墓じまいの補助金の申請者は、現在そのお墓を管理している人(墓地使用者)またはその親族に限定されているケースがほとんどです。
たとえば、墓地の名義人本人やその配偶者、または承継して管理している子ども等が、補助金の申請対象となります。
名義変更がされていない場合や、すでに親族全員が他界しているケースでは、法的な整理や委任状等の手続きが必要になる場合があります。
■ 団体(寺院・自治会等)が申請する場合 地域によっては、寺院や自治会等の団体が、まとめて墓じまいの補助金を申請出来る制度もあります。
これは、無縁墓の整理や共同墓地の統合・再整備を目的としたものが多く、個人とは異なる枠組みで支給される事が特徴です。
団体申請の場合には、一定数以上の合意や会議記録、地域住民の同意書等が必要になる場合もあり、申請のハードルは若干高くなる傾向があります。
■ 居住地との関係に注意 墓じまいの補助金は、申請者がその自治体に居住している事(住民票がある事)を条件としているケースが多いです。
たとえば、実家の墓はA市にあるけれど、現在はB市に住んでいるという場合、A市の補助金を申請出来ない事があります。
一方で、墓地の所在地ではなく、申請者の居住地に補助制度があるパターンもある為、どちらの自治体に補助金制度があるかを確認する事が重要です。
■ 所得や年齢が条件になる事も 一部の自治体では、生活保護を受けられてる一定の年齢以上(例:70歳以上)所得制限を満たす方等、申請者の経済状況に応じた条件が設定されている事もあります。
その為、墓じまいの補助金の利用を検討している場合は、事前に自治体の公式サイトや窓口で最新の条件を確認する事が不可欠です。
これらの事を考えていく事は、人生の節目における大切な選択です。
墓じまいの補助金の制度を活用する事で、経済的な負担を軽減し、スムーズに次の供養の形へとつなげる事が出来るでしょう。
対象となる費用の範囲は?(撤去費・改葬費等)
墓じまいの補助金を申請する際に特に注意したいのが、補助の対象となる費用の範囲です。全ての費用が補助されるわけではなく、自治体ごとに対象となる項目が明確に定められている為、事前の確認が欠かせません。
■ 墓石の撤去・処分費用 もっとも一般的に墓じまいの補助金の対象とされるのが、墓石の解体・撤去に掛かる費用です。
これには、重機の使用料、搬出作業費、墓石の廃棄や処分に関わる費用等が含まれます。
墓の大きさや立地条件によって金額は異なりますが、10万円〜30万円程度が相場とされ、この部分に対して補助金が交付されるケースが多いです。
■ 改葬に掛かる費用(永代供養・納骨費等) お墓を閉じた後、遺骨を新たな供養先へと移す必要があります。
その際に掛かる、改葬先の永代供養料や納骨堂の契約費、合祀墓への埋葬費用等も補助対象となる事があります。
ただし、改葬先が公的な施設や、自治体が指定した寺院等に限られている場合もある為、申請前に詳細を確認しましょう。
■ 行政手続きに関する費用 改葬許可申請書の取得や提出等、行政手続きが必要です。
これに伴う証明書発行手数料や代行業者への依頼費も、自治体によっては補助対象となる事があります。
特に高齢者や一人暮らしの方で、手続きが困難なケースでは、申請サポートを含む業者への依頼費用が補助される例もあります。
■ 宗教儀式・法要費用は対象外が基本 注意が必要なのは、手配の際に行われる閉眼供養(魂抜き)や僧侶へのお布施、お車代等の宗教儀式関連の費用は、補助金の対象外である事が一般的です。
これらは個人的・宗教的な支出とされ、公的資金の用途から外れる為、自己負担になる事が多いと認識しておきましょう。
■ 補助金の上限額にも注意 また、補助される金額は、上限設定されているケースがほとんどです。
たとえば、上限5万円まで費用の2分の1まで補助といった形式が多く見られます。
その為、総額と補助金の支給額の差額は自己負担になる事を踏まえた資金計画が重要です。
このように、墓じまいの補助金で補助される費用の範囲は多岐にわたりますが、全てをカバー出来るわけではありません。
必ず自治体の要綱や申請書類を確認し、対象となる費用と対象外の項目を把握しておきましょう。
墓じまいの補助金・申請方法と手続きの流れ

墓じまいの補助金を活用するには、適切な手続きと書類の提出が必要です。
補助金の申請は一度で完了するものではなく、いくつかのステップを踏んで進める必要がある為、全体の流れを把握しておく事が大切です。
ここでは一般的な自治体における申請から補助金受給までの基本的な手続きの流れを紹介します。
■ ステップ1|自治体の制度を確認する まず最初に行うべきは、お住まいの自治体、または墓地がある自治体に墓じまいの補助金の制度があるかを確認する事です。
自治体によって制度の有無や内容、申請時期、必要書類が異なる為、公式サイトや窓口に問い合わせて、最新の情報を収集しましょう。
■ ステップ2|墓じまいの計画と見積書の取得 墓じまいの補助金申請には、作業に掛かる見積書の提出が必要なケースが多くあります。
その為、墓石の撤去や改葬を行ってくれる業者に依頼し、事前に作業内容と金額の見積もりを取得しておきましょう。
※一部の自治体では、指定業者のみが対象となる場合がある為、業者選びにも注意が必要です。
■ ステップ3|必要書類をそろえる 多くの自治体で求められる主な書類は以下の通りです:
墓じまいの補助金を貰う為の申請書(自治体の所定用紙)
墓地の使用許可証の写し
一連の作業をするにあたっての見積書または領収書
改葬許可証や改葬先の契約書(納骨堂や永代供養先等)
身分証明書の写し
振込先口座情報(補助金の振込用)
申請時点で改葬許可証の写しが必要なケースと、工事完了後の実績報告として提出するケースの2通りがあります。
■ ステップ4|自治体へ申請書を提出 必要書類が揃ったら、自治体の担当窓口(多くは市民課または環境課等)に申請書一式を提出します。
郵送または窓口提出が一般的で、自治体によっては事前予約制やオンライン受付に対応しているところもあります。
■ ステップ5|審査と決定通知 書類が受理されると、自治体による審査が行われます。
審査期間は1週間〜1ヶ月程度が目安で、問題がなければ補助金交付決定通知書が届きます。
この通知をもって、正式に補助対象と認められ、工事や改葬を進めていく事になります。
■ ステップ6|工事完了後の実績報告 工事完了後には、実施内容の報告書や領収書の写し、完了写真等を添えて実績報告を提出します。
これにより最終的な支給額が確定し、後日、指定口座に補助金が振り込まれます。
余裕を持って準備する事が大事
墓じまいの補助金の申請には、書類の不備や認定条件の見落とし等によって申請が却下されるケースもあります。その為、早めに準備を始め、自治体の窓口と相談しながら進める事が成功のカギとなります。
必要書類一覧と提出先
墓じまいの補助金を申請する際には、所定の申請書類を漏れなく準備し、指定の窓口に提出する必要があります。書類の不備や記載ミスがあると、審査がスムーズに進まないばかりか、申請そのものが受理されないケースもある為、慎重な確認が重要です。
ここでは一般的に多くの自治体で求められる必要書類の一覧と、提出先の基本的な情報をわかりやすくご紹介します。
■ 墓じまいの補助金の申請に必要な書類一覧(例)
墓じまい補助金交付申請書
自治体が提供する所定の用紙。多くは公式サイトからダウンロード可能です。
墓地使用許可証の写し お墓の使用権を証明する書類。使用者本人または承継者が対象である事を確認する為に必要です。
墓石撤去・解体の見積書または請求書の写し 補助対象費用を確認する為の根拠資料。見積りの段階でも申請可能な自治体が多いですが、工事完了後に差し替えを求められる事もあります。
改葬許可証の写し 遺骨を移す為に必要な公的許可証。市区町村の役所で発行されます。
改葬先との契約書や使用許可証の写し 新しい納骨先(納骨堂・永代供養墓等)の契約内容を証明する書類です。
本人確認書類の写し 運転免許証や健康保険証・マイナンバーカード等が必要。
振込口座情報 補助金の振込先となる金融機関の通帳の写し等を求められる場合があります。
その他、自治体が指定する書類
…例えば、委任状(名義人と申請者が異なる場合)、承諾書、工事完了報告書等。
※自治体によっては、これら以外の書類や独自の様式を求める場合もあります。
申請前に必ず公式情報を確認して下さい。
■ 書類の提出先と注意点
墓じまいの補助金の書類提出先は、各市町村の役所・役場の担当課になります。
具体的には以下のような部署が多く担当しています。
環境衛生課、市民生活課、福祉課、高齢福祉課、生活支援課
各自治体で担当課の名称が異なる為、墓じまいの補助金の窓口はどこか、役所に事前確認をするのが確実です。
また、提出方法も窓口持参のみ郵送も可事前予約制等自治体ごとに異なる為、提出前に電話やメールで問い合わせておく事が安心です。
適切な書類を正しく揃えて提出する事が、墓じまいの補助金を確実に受け取る為の第一歩です。
書類準備が不安な場合は、地域の石材店や行政書士、または自治体の市民相談窓口等を活用して、サポートを受けるのも一つの方法です。
必要書類一覧と提出先
墓じまいの補助金の制度を活用するにあたっては、申請から補助金の受給までにどの程度の時間が掛かるのか、どこに注意すべきかをあらかじめ把握しておく事が大切です。補助金の支給には書類審査や現地確認、完了報告等複数のステップが必要となる為、早めの行動と丁寧な準備が成功のカギとなります。
■ 申請から受給までの一般的な期間 事前相談・申請書提出
→ 自治体へ制度の有無を確認し、必要書類を提出。
所要期間:1週間~数週間(書類の準備・取り寄せ等含む)
自治体による審査・交付決定通知 → 内容に問題がなければ交付決定通知書が届く。
所要期間:2週間~1ヶ月程度
墓じまい・改葬工事の実施 → 墓石の撤去や遺骨の移転を業者に依頼して実施。
所要期間:1日~数週間(工事規模・業者の混み具合による)
完了報告・実績書類の提出 → 工事後、写真・領収書・報告書等を提出する。
所要期間:1週間程度
補助金の振込(受給) → 書類に問題がなければ、指定口座へ振込。
所要期間:2週間~1ヶ月
合計の目安期間:早くて1.5ヶ月、通常は2〜3ヶ月程度
※年度末等の繁忙期や書類不備がある場合は、さらに時間が掛かる事があります。
■ よくある注意点と対策
書類の不備・記入漏れ → 最も多いトラブル。
自治体によっては形式や添付資料に細かい指定がある為、提出前に必ずチェックリストで確認を。
工事前に交付決定を受けていない → 多くの自治体では、補助金の交付が決定される前に工事を始めてしまうと、補助対象外になる可能性があります。
→ 必ず交付決定通知書を受け取ってから作業を進めましょう。
改葬先の書類が未整備 → 永代供養先や納骨堂との契約が不十分だったり、証明書がない場合は申請が通らないケースも。事前に改葬先を確定させましょう。
予算に上限がある自治体も多い → 先着順年度内に予算枠が埋まり次第終了といったケースもある為、早めの申請が有利です。
墓じまいの補助金は、制度を正しく理解し、スケジュールと準備をしっかり整えれば、経済的な負担を大きく軽減出来る貴重な支援制度です。
スムーズな申請・受給の為には、余裕を持った計画と自治体との綿密なやり取りがポイントとなります。
よくある申請ミスとその対策
墓じまいの補助金の申請は、手順さえ守れば難しいものではありませんが、些細なミスによって不受理や減額、支給不可になるケースも少なくありません。ここでは申請時にありがちなトラブルやミスの例と、その具体的な対策方法について解説します。
■ ミス①:交付決定前に墓じまい工事を始めてしまう もっとも多い失敗が、補助金の交付決定を受ける前に、工事や改葬を始めてしまうケースです。
早く進めたいという気持ちは理解できますが、補助金制度では、事前承認を受ける事が大前提になっている為、工事後の申請では対象外となる可能性が高くなります。
対策:必ず“交付決定通知書”を受け取ってから工事を開始する。
■ ミス②:必要書類の不備や記載ミス 書類の押印漏れ・記入漏れ・添付資料不足も非常に多い申請ミスのひとつです。
特に多いのは、以下のような不備です。
見積書や請求書に工事内容の詳細が記載されていない
改葬先の情報が不明確(契約書が添付されていない)
名義人と申請者が異なるのに委任状がない
対策:提出前に自治体のチェックリストを使い、第三者にも確認して貰うと安心。
■ ミス③:改葬先が未確定、または証明書がない お墓を辞める事は、遺骨をただ取り出して終わりではありません。必ず改葬先(納骨堂、永代供養墓等)が確定しており、証明書類がある事が補助金の条件です。
改葬先の契約が曖昧だったり、必要書類が出せないと、補助金が下りない可能性があります。
対策:事前に改葬先の契約を済ませ、契約書や永代使用証明書等をしっかり準備しておく。
■ ミス④:申請期限を過ぎてしまう 自治体によっては、年度内に申請する事工事完了から、◯日以内に報告書提出といった期限のルールが厳密に定められている場合があります。
これを見落としてしまうと、せっかくの墓じまいの補助金も受給できません。
対策:申請から報告までのスケジュールを、カレンダーやタスク表で管理しておく。
■ ミス⑤:申請出来る人の条件を満たしていない 墓じまいの補助金は、墓地の所在地の住民である事や、墓地の使用権者である事等、申請者に明確な条件があるケースがほとんどです。
条件を満たしていない人が申請しても、原則受理されません。
対策:申請前に“自分が対象者に該当しているか”を自治体窓口で確認する。
丁寧な準備が、確実な補助金受給につながる
墓じまいの補助金を活用する上で大切なのは、あせらず、慎重に一つひとつ確認しながら進める事です。補助金を受け取れるかどうかで、負担額が大きく変わる為、ミスを防ぐ事は金銭面・精神面どちらにおいても大きな意味があります。
墓じまいの補助金がもらえる地域・もらえない地域

墓じまいの補助金は、全国どこでも一律に支給される制度ではありません。
その為、自分の住んでいる地域、あるいはお墓のある地域では補助金が出るのか?という点は、多くの方が最初にぶつかる疑問です。
ここでは墓じまいの補助金を実施している地域・していない地域の傾向や、自治体ごとの対応状況を詳しくご案内します。
■ 墓じまいの補助金がもらえる地域の特徴とは?
墓じまいの補助金を導入している自治体には、いくつか共通した傾向があります。
① 過疎化・高齢化が進んでいる地方自治体 地方では、無縁墓の増加が社会問題になっている為、促進していく事で地域の墓地整備や環境改善につなげたいという意図から、補助金制度を積極的に導入しているケースが多いです。
例えば、岐阜県高山市、熊本県人吉市、北海道上川町等では、過疎化や高齢化が進んでいってます。
② 墓地管理に関する条例や施策が整備されている自治体 条例で墓じまい手続きや改葬支援の仕組みを明文化している自治体では、補助金の導入も進んでいます。
こうした自治体は、市民サービスとして丁寧な情報提供も行っているのが特徴です。
■ 墓じまいの補助金がもらえない地域の特徴 一方で、補助金を導入していない地域にも一定の傾向があります。
① 都市部の自治体(例:東京23区・大阪市等) 人口が多く、墓地管理がある程度整備されている都市部では、補助金制度を設けていないところもあります。
また、都市部では墓じまいに関するトラブルが少ない為、公的な支援が必要とされていないという背景もあります。
② 民間墓地が多く、行政が関与しづらいエリア 民営霊園が主流となっている地域では、墓地の管理が自治体ではなく事業者によって行われる為、行政として補助金の支給に関与しない方針を取っている場合があります。
■ 自分の地域の補助金制度を確認する方法 墓じまいの補助金が利用出来るかどうか、各自治体のHP、それから市民課・環境衛生課等の窓口で確認するのが最も確実です。
以下の方法で調べるのが効果的です
「〇〇市 墓じまいの補助金」というあなたのお住い地域名キーワードで検索
自治体の公式HPで生活環境環境政策課等のページを探す
電話で直接問い合わせる(担当課に繋いで貰う)
また、地元の石材店や葬儀社が、補助金制度の有無や申請サポートを熟知している場合もある為、地域密着の業者に相談してみるのも有効です。
■ 墓じまいの補助金がない地域でも出来る事 もし自分の地域に補助金制度がない場合でも、以下のような方法で費用を抑える工夫が可能です。
複数の石材業者から相見積もりを取る
納骨堂や合祀墓等、低コストな改葬先を選ぶ
自治体主催の改葬合同事業等の情報を探す
制度がないからといって、あきらめる必要はありません。自治体に相談する事で、他の支援策や紹介先を案内してもらえる場合もあります。
市町村によって違う補助金制度
墓じまいの補助金は、国や都道府県単位で定められた統一制度ではなく、各市町村が独自に設けている制度です。その為、支給額や申請条件、対象費用の範囲等が自治体ごとに大きく異なります。
ここでは市町村によって異なる補助金制度の代表的な違いを項目ごとに詳しく見ていきましょう。
■ 支給額の違い 自治体によって補助金の上限額や補助割合(何割まで出るか)が異なります。
A市:上限5万円、費用の1/2まで補助
B町:一律3万円支給(条件を満たせば固定額)
C村:1基あたり最大10万円まで(撤去費+改葬費の合算)
金額だけを見るとC村のように高額補助の自治体もありますが、その分審査が厳しい、書類が多いといった傾向もあります。
■ 対象となる費用の違い ある自治体では墓石の撤去費用のみが対象であるのに対し、別の自治体では改葬費・永代供養費・書類作成費等も含めて広く支給されるケースもあります。
例
D市:墓石撤去と改葬費用が補助対象
E町:撤去のみ対象、永代供養費は対象外
F村:業者への事務代行費や交通費も一部対象
■ 対象者の条件の違い
墓じまいの補助金を申請出来る対象者についても市町村で差があります。
G市:墓地の所在地に住民票がある人のみ対象
H町:申請者の居住地が町内であればOK(墓地の場所は問わない)
I村:65歳以上の高齢者のみを対象とする独自条件あり
また、補助金を受け取る為には、過去に同様の支援を受けていない事を条件としている市町村もあります。
■ 申請方法や期限の違い J市:通年受付、工事前申請必須
K町:年2回の募集期間のみ(4月・10月)
L村:郵送受付不可、窓口持参のみ対応
このように、申請タイミングを逃すと一年待たなければならない自治体もある為、早めのスケジュール確認が重要です。
■ 制度の違いを知る事で賢く利用出来る このように墓じまいの補助金は市町村によって制度設計がバラバラなので、他の地域では補助が出たから、うちも出るはずと思い込むのは危険です。
必ず、該当する自治体に直接確認し、最新の制度概要や条件、必要書類を把握したうえで進めるようにしましょう。
実際に補助金を出している自治体の事例紹介(例:大阪市・札幌市等)
この制度は、全国的に少しずつ導入が進んでいるものの、実際にどの自治体がどのような内容で支給しているのかは、あまり知られていません。ここでは実際に墓じまいの補助金を提供している一部の自治体の具体的な制度内容をご紹介します。
どういった支援があるのかを知る事で、自分の地域との比較や検討に役立てる事ができます。
■ 大阪市(大阪府) 大阪市では、直接墓じまいの補助金という名目ではなくても、地域によっては高齢者や生活困窮者を対象に、改葬・永代供養費への助成制度を設けている区が存在します。
支援対象:区によって異なるが、高齢者・生活保護世帯等
支援内容:改葬費・永代供養料の一部助成
申請方法:福祉課や高齢福祉課に事前相談が必要
大阪市は区ごとの裁量が強い為、西成区や住之江区等、一部の地域で独自の支援を実施している場合があります。
■ 札幌市(北海道) 札幌市では、高齢者福祉事業の一環として、費用の助成制度を展開している事例があります。
対象者:札幌市在住で一定年齢以上の方
補助金額:上限5万円(工事費や改葬費を含む)
条件:改葬先が明確である事、事前申請である事
札幌市では、生活支援としてのエンディングサポートに力を入れており、相談窓口も充実しています。
■ 飛騨市(岐阜県) 岐阜県の飛騨市では、少子高齢化・無縁墓対策として、全国に先駆けて制度としての墓じまいの補助金を明文化しています。
補助金額:上限10万円(費用の1/2まで)
対象:市内にある無縁化の恐れがある墓地
提出書類:見積書、写真、改葬許可証等
地域ぐるみで墓地の整理整備を推進しており、個人だけでなく自治会等も対象になる場合があります。
■ 人吉市(熊本県) 熊本県人吉市では、災害被害を受けた墓地の復旧とあわせて、費用も補助対象としています。
特徴:災害支援と連動した補助金制度
対象:市内の被災墓地で、移転・撤去を行うもの
補助内容:撤去費、改葬費、運搬費等を助成
このように、地域事情(高齢化・災害・無縁墓問題)に応じた支援策としての墓じまいの補助金が存在しています。
■ 制度は随時変動する為“最新情報の確認”が必須 補助金制度は、年度ごとに内容が見直されたり、予算の都合で急に終了・縮小される事もあります。
その為、昨年は支給されたから今年もあるだろうと思い込まず、最新の情報を必ず公式サイトや担当窓口で確認する事が大切です。
また、各自治体、場合によってはホームページに補助金制度が掲載されていない事もある為、電話で直接問い合わせる事が確実です。
補助金がない場合の対処法とは?
墓じまいの補助金は非常にありがたい制度ですが、全ての市区町村に用意されているわけではありません。調べてみた結果、自分の地域には制度がなかった…という方も多い事でしょう。
しかし補助金がない場合でも、経済的負担を軽減しながら行う方法はいくつかあります。
ここではその具体的な対処法をご紹介します。
■ ① 相見積もりを取る、費用を比較する 補助金がない場合、まず出来るコストダウンの第一歩は複数業者からの相見積もりです。
同じ作業内容でも、業者によって費用に数万円〜十数万円の差が出る事もよくあります。
ポイント:
墓地の場所や広さ、撤去方法によって金額が変動する為、現地調査を含む見積もりを取るのが理想
専門業者、地元の石材店、葬儀社等を比較対象にする
追加費用の有無や改葬費用が含まれているか等もチェック
■ ② 改葬先を工夫して費用を抑える 掛かる費用の中で、改葬先の選択もコストに大きな影響を与えます。
例えば、一般的な霊園よりも永代供養墓や合祀墓の方が費用を抑えやすい傾向にあります。
✅ コストを抑える改葬先の例
寺院の共同墓(5〜10万円)
自治体が運営する合祀墓や納骨堂
海洋散骨や手元供養等の新しい供養形態
※改葬先によっては宗教・宗派の制限がある為、事前に確認しましょう。
■ ③ 葬儀社や石材店のセットプランを利用する 最近では、墓じまい+改葬+永代供養をセットにしたパッケージプランを提供している業者も増えており、個別に依頼するよりも割安になるケースがあります。
また、地元の葬儀社や石材店の中には、地域の事情に詳しく、補助金の代わりに独自割引や分割払いを用意している業者もある為、相談してみる価値はあります。
■ ④ NPO・市民団体に相談する 一部の地域では、墓じまいや改葬を支援するNPO法人や地域団体が活動しており、無料相談や手続き代行等のサポートを行っています。
例
生前整理・遺品整理をサポートする団体
高齢者のエンディングサポートを行うNPO
地域包括支援センター等
特に高齢の方や一人暮らしの方は、手続きの負担を軽減出来るうえ、精神的な安心感にもつながります。
■ ⑤ 費用の一部を終活費用として積立・準備しておく 今すぐではないが、将来的に考えているという方は、早めに費用の目安を把握し、少しずつ積み立てておくのも有効な対策です。
金融機関によっては、終活費用積立プラン等を設けている場合もあります。
■ 補助金がなくても、納得出来る形で実現出来る 墓じまいの補助金がないからといって、決してあきらめる必要はありません。
工夫次第で費用を抑えたり、安心して手続きを進めたりする方法は十分にあります。
経済的な負担を出来るだけ少なくしながら、大切なご先祖の供養を丁寧に行う為にも、早めに情報を集め、信頼出来る相談先を見つけておく事が重要です。
墓じまいの補助金を活用した人の事例と体験談
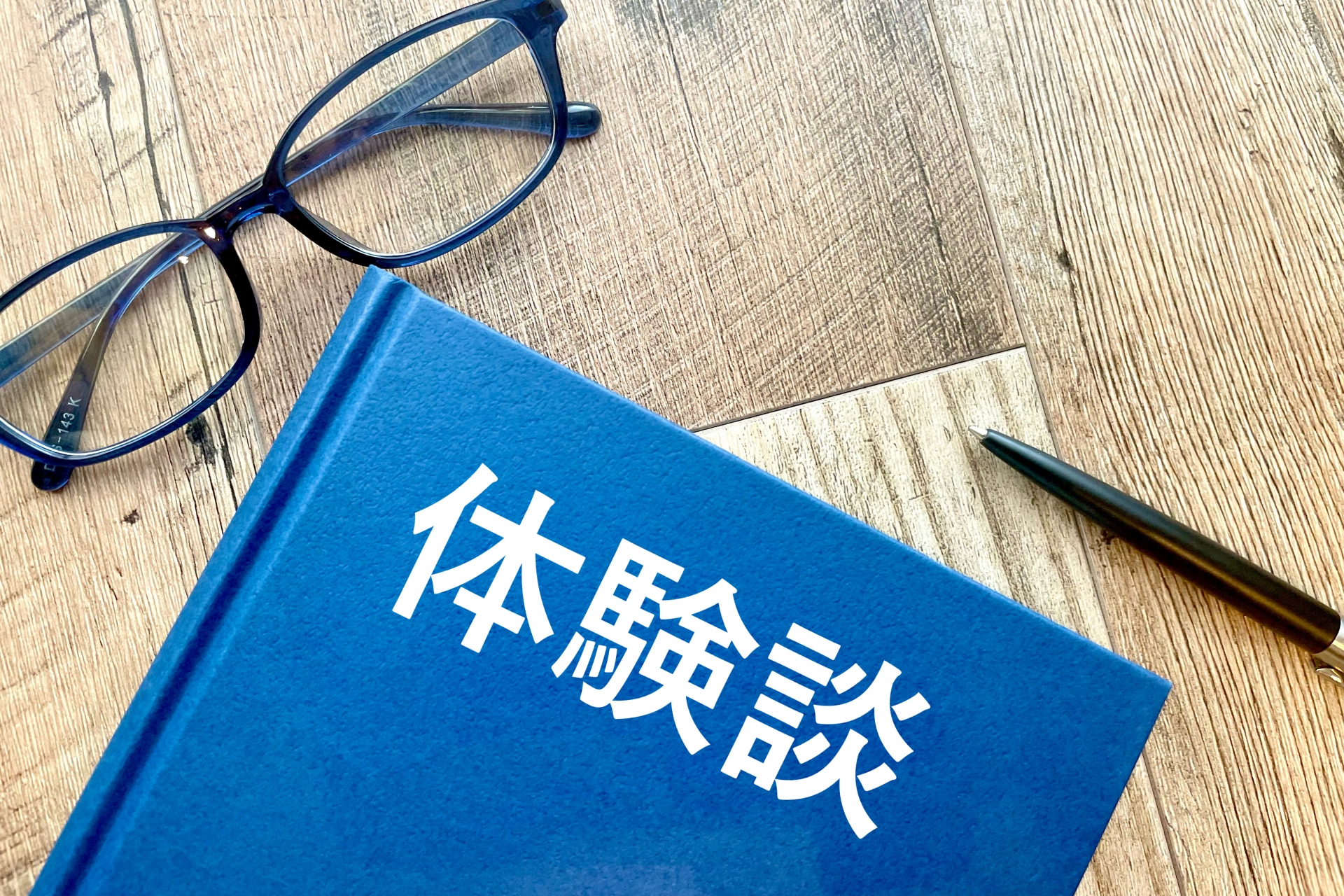
墓じまいの補助金は、うまく活用すれば経済的な負担を大きく減らせる貴重な制度です。
実際に行った人たちは、どのような経験をし、どのような点に満足したのでしょうか。
ここでは墓じまいで補助金を活用したリアルな事例や体験談を紹介します。これから申請を考えている方にとって、参考になるポイントが満載です。
 1.岐阜県高山市 70代女性
1.岐阜県高山市 70代女性■ 事例1|補助金を活用して、スムーズにできたケース
支給額:約7万円(撤去費用の一部として)
両親が建てたお墓を守ってきましたが、自分に子どもがいない為、墓じまいを決意しました。
費用面が心配でしたが、高山市に墓じまいの補助金の制度があると知って、申請しました。
手続きは少し大変でしたが、市役所の担当者が丁寧に教えてくれたので安心できました。
結果的に、補助金で費用負担が軽くなり、無理なく改葬先を用意する事ができました。
ポイント:自治体窓口でのサポートを受けるとスムーズに申請出来る。
 2.北海道札幌市 60代男性
2.北海道札幌市 60代男性■ 事例2|補助金がもらえるタイミングに注意
支給額:約5万円
父親の墓じまいをする事になり、札幌市の墓じまいの補助金を使いました。
しかし最初、工事を急ぎすぎて交付決定通知を受ける前に業者に作業を依頼してしまい、危うく補助対象外になるところでした。
幸いにも事前に相談していた為、着工を待って交付決定を受ける事ができました。
この経験から、補助金申請はスケジュール管理が本当に大切だと痛感しました。
✅ ポイント:交付決定前に工事を始めない事が鉄則!
 3.大阪府堺市 50代女性
3.大阪府堺市 50代女性■ 事例3|補助金がない地域でも工夫して乗り切ったケース(補助金制度なし)
私の住む堺市では、残念ながら墓じまいの補助金はありませんでした。
ですが、石材店を3社比較して一番安く、丁寧な対応をしてくれる業者に依頼する事で、想定よりも10万円以上コストダウンできました。
また、永代供養墓を選んだ事で改葬費用も抑える事ができ、全体の負担を最小限に抑える事ができました。
✅ ポイント:補助金がなくても、業者選びや改葬先で費用負担を減らす工夫が出来る。
■ まとめ|体験談から学べる成功のコツ 事前に自治体の制度をしっかり確認する
交付決定前には絶対に工事を始めない
業者選びや改葬先を工夫してコストを抑える
墓じまいの補助金は、うまく活用できれば大きなサポートになります。
成功者たちの体験談を参考にしながら、慎重かつ計画的に進めていく事が、後悔のない墓じまいにつながるでしょう。
まとめ|墓じまいの補助金は賢く使えば負担軽減につながる
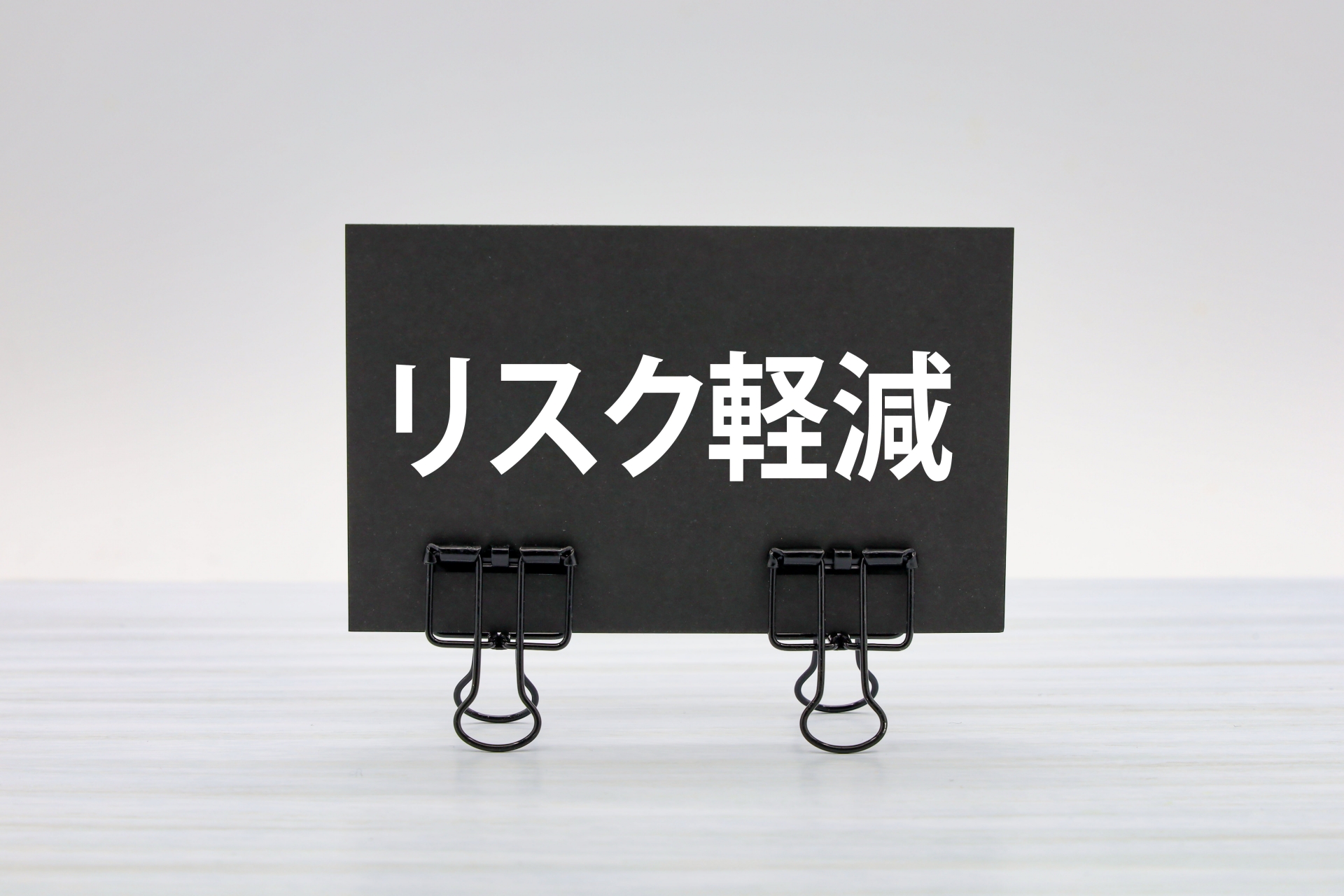
墓じまいの補助金は、墓じまいに伴う経済的負担を大きく軽減出来る、非常に心強い制度です。
しかし制度の有無や内容は自治体ごとに異なり、申請のタイミングや手続きにも注意が必要です。
墓じまいを検討している方は、まず自分の地域や墓地所在地の自治体に墓じまいの補助金があるかどうかを調べ、条件や申請方法を正確に把握する事が大切です。
もし補助金制度がない場合でも、相見積もりや改葬先の工夫等によって、負担を抑える方法は十分にあります。
実際に墓じまいの補助金を活用した方たちの体験談にもあったように、早めの情報収集や正しい手続き。
信頼出来る相談先の確保等、これらを意識するだけで、安心して墓じまいを進める事が出来るでしょう。
墓じまいは、ご先祖様への感謝と未来への責任を果たす大切な決断です。
補助金制度を賢く活用し、経済的にも精神的にも納得のいく墓じまいを実現して下さい。
まずは自治体の情報を調べよう
墓じまいの補助金を活用する第一歩は、お住まいの自治体、またはお墓の所在地にある自治体の制度を正しく把握する事から始まります。この補助金制度は国レベルではなく、各市区町村が独自に設けている為、地域によって内容や有無が大きく異なってくるのが現実です。
■ 自治体によって制度の有無も中身も違う 同じ都道府県内であっても、墓じまいの補助金がある自治体と、まったく制度がない自治体が混在しています。
さらに、補助金の対象者・対象費用・支給額・申請期限等も異なる為、“どこの情報を参考にするか”がとても重要になります。
たとえば:
A市では墓石撤去費のみ補助対象
B町では永代供養費や書類作成代までカバー
C村では年に1回しか申請受付をしていない
このような違いがある為、ネット検索や噂だけに頼らず、必ず公式情報を確認する事が大切です。
■ 具体的な調べ方|3つのおすすめ方法 自治体の公式ホームページで確認
〇〇市 墓じまいの補助金と検索すると、該当する制度ページが出てくる場合があります。
生活環境課環境衛生課高齢福祉課等のページに記載されている事が多いです。
役所の担当窓口へ直接問い合わせる
ホームページに記載がない場合もある為、電話やメールで直接問い合わせてみるのが確実です。
担当部署がわからなくても、墓じまいの補助金制度について相談したいと伝えれば、適切な窓口につないでもらえます。
地元の石材店や葬儀社に聞いてみる
地域密着の業者は、自治体の制度を熟知している事が多く、申請のサポートをしてくれるケースもあります。
補助金を使ってしたいと伝えると、親切に教えてくれる事が少なくありません。
■ 情報収集のタイミングが成功のカギ 墓じまいの補助金の多くは、申請前に事前相談や交付決定が必要です。
先に工事を始めてしまうと、たとえ条件を満たしていても補助金が支給されない場合もあったりします。
その為、まずは自治体の情報収集から始める事が、経済的にも精神的にも安心して進める為のポイントです。
一生に一度あるかないかの大きな決断です。
だからこそ、補助金という公的制度を正しく活用する為にも、情報収集のスタート地点は“自治体を調べる事”から始めましょう。
相談先やサポート機関を上手に活用する方法
墓じまいの補助金を検討する際、自分ひとりで全ての情報を集めて申請手続きを進めようとすると、思いのほか時間や労力がかかってしまいます。特に初めて墓じまいを行う方にとっては、必要書類の準備や申請手続き、改葬先の選定等、多くの判断を伴う為、不安になる場面も多いでしょう。
そこでおすすめなのが、信頼出来る相談先やサポート機関を上手に活用する事です。
以下に、墓じまいの補助金の申請や実施にあたり、頼りになる相談先をご紹介します。
■ 自治体の担当窓口(市役所・町役場) 墓じまいの補助金があるかどうかを確認出来るところでもありますが、申請書類の書き方、必要な添付書類、申請スケジュール等を丁寧に案内してくれるのが自治体窓口です。
多くの場合、環境課生活環境課市民課福祉課等が担当部署となっています。
こんな時におすすめ
補助金制度の詳細を知りたい
書類を自分で揃えたいが内容に不安がある
手続きの期限やルールを確認したい
■ 地元の石材店・墓じまい専門業者 多くの石材店や墓じまい専門業者は、自治体の補助金制度や申請サポートに精通しています。
中には補助金の申請代行や必要書類一式の用意改葬先の紹介等、ワンストップで対応してくれる業者もあり、特に高齢者の方には心強い味方になります。
こんな時におすすめ
書類の準備や手続きに自信がない
補助金を使って墓じまい全体を効率的に進めたい
複数の業者を比較検討したい
■ 行政書士や終活カウンセラー 墓じまいの補助金の手続きが煩雑に感じる場合や、親族間の同意等法律的な配慮が必要なケースでは、行政書士等専門家の力を借りるのも有効です。
また、終活カウンセラー等に相談すれば、将来設計も含めたアドバイスを受けられるメリットがあります。
こんな時におすすめ
相続人が複数いて合意形成に不安がある
墓じまいと一緒に生前整理や遺言も検討している
手続きの代行を全て任せたい
■ NPO法人や地域包括支援センター 高齢者や一人暮らしの方を対象に、墓じまいや供養についての無料相談や情報提供を行っているNPO法人や地域の支援団体もあります。
中には、自治体と連携して補助金の制度利用サポートや改葬先の紹介等を行っている団体もあります。
この記事を書いてるNPO法人いきいきつながる会がまさにこの墓じまいを業務として行っております。
小さな事でもご相談下さい。
お問い合わせは以下よりどうぞ。
こんな時におすすめ
相談相手が周囲におらず、不安が大きい
経済的に不安がある
地域の事情に詳しい支援機関を利用したい
等現在お悩みの事ありましたら、可能な限りご相談対応させて頂きますので、以下フォームよりお問い合わせ下さい。